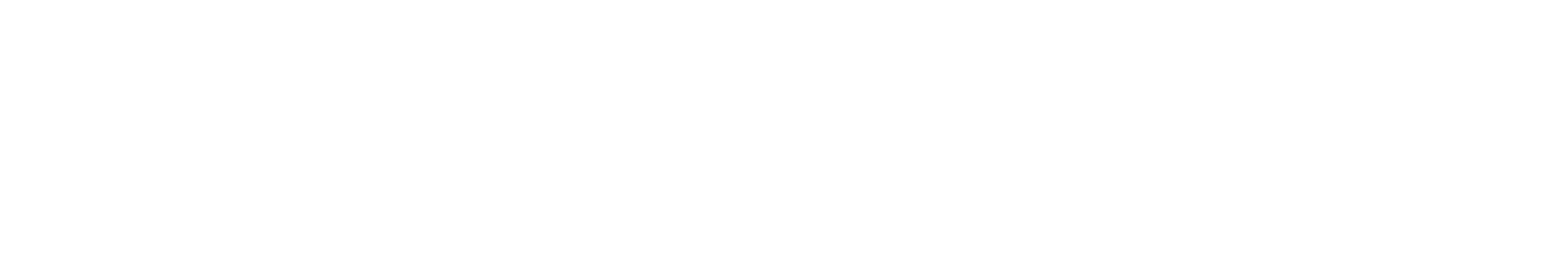2024年読んだ本リスト
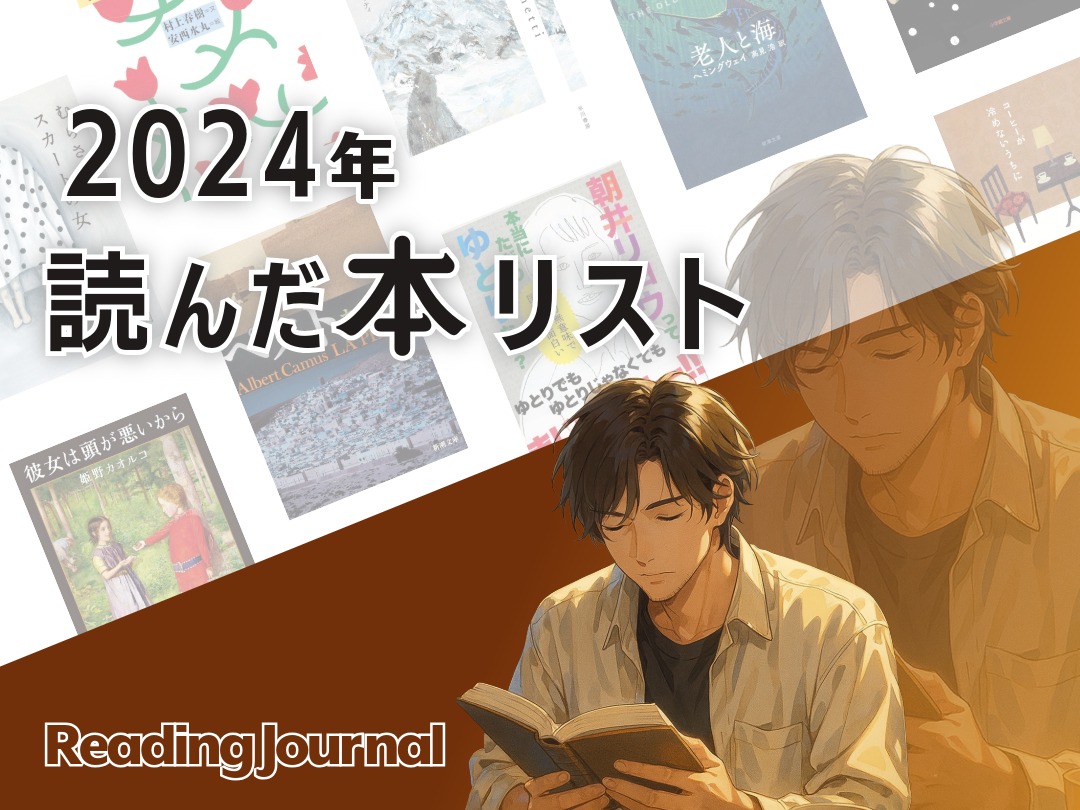
2024年に読んだ本をリストにしました。1冊ずつ丁寧に深掘りはできませんが、簡単な紹介で気になった本をチェックしてもらえたら幸いです。
ジャンルは小説、エッセイ、漫画、ビジネス書、自己啓発、技術書など多岐にわたります。
2024年 読んだ本ベスト5

“俺”と友人シャルリーの日常が静かに淡々と茶色に蝕まれていく様子が描かれます。
シャルリーは飼っている犬を安楽死させなければいけませんでした。ペット特別措置法によって茶色以外のペットを飼ってはいけないからです。始まりは増えすぎた猫を規制するための法律でした。茶色を残す理由は都市生活に適していると国の科学者が主張するから。
さらに。ペット特別措置法に対する批判的な記事を書いた『街の日常』という新聞が廃刊に。新聞を読みたかったら『茶色新報』しかない。図書館や本屋の棚から多くの本が消え、メディアも茶色に染まっていき、ついには朝までも茶色になっていく。

本の構成はたった14ページの物語と、巻末に東大名誉教授のメッセージと称した解説が載っています。実質この解説のほうがメインとなっていて、ここで作者が伝えたかったことを分かりやすくまとめていました。
主人公の”俺”は新しい法律に違和感や、妙な感じ、言い足りないこと、もやもやを常に抱えていました。心の奥では世の中が良くない方向に行こうとしてるのを察知しているのに、それをあらゆる言い訳や権力への従属姿勢において諦めていく姿が描かれています。
全体主義に対する警鐘を鳴らす本ですが、声高に糾弾するのではなく、”俺”とシャルリーの日常が静かに蝕まれていく恐ろしさを淡々とした筆致で綴っています。
つまり我々が政治に無関心であり続けることが、社会をより悪い方向に促す一手を担ってしまっている可能性があるわけで、国民すべての人に関係がある話です。日本も茶色に染まっていく可能性はあるわけで、決して他人事のような話ではありません。すでに大きな間違いを犯す萌芽を、私たちは見過ごしてしまっているのかもしれません。
出版当時のフランスでは、全体主義に対する危機感をより多くの、とくに若者に知ってもらうために印税を放棄してわずか1ユーロで発売されていました。

ヴィンセント・ギャロのイラストは、表紙のほかに本編中に多く挿入されています。物語に合わせて、ギャロの絵が全体主義の静かに迫ってくる不穏な空気間を表現しているかのようでした。


アメリカのカリフォルニアを舞台に、ジョージとレニー、二人の渡り労働者と農場での人間模様を追った物語。
小柄だが頭がきれて口がよく回るジョージと、体はでかいが幼児レベルの知能しかないレニー、対極にある2人が農場を転々と渡り歩きます。2人に友情があるのは確かだが、どこか互いに依存してる部分があったり、不安定な関係であることが感じとれます。
農場の老人、臭い犬、頼れる青年、ボスの息子とビッチな女、黒人の馬屋係。農場を取り巻く人間模様と重大な事件が、将来農場を持つ夢を抱くジョージとレニーの2人に残酷な現実を突きつけます。

農場内のそれぞれの人間性を引き出しながら世界観を作り出している本書。ずっと農場にいるのに、仕事をしている描写は一切ありません。仕事が終わった後の、労働者たちが飯場で賑やかにしている雰囲気だけで、作品全体の輪郭を作ってます。
一貫して外面描写に徹しているので、人物の思ったことや感じたとった主観的な内面描写はありません。そのため淡々とした筆致にはなりますが、ジョージとレニーの友情や夢への渇望など、農場で働く人々の人間模様が生彩に描かれています。
最期まで読んでわかるこの話の切なさとやるせなさ、ジョージとレニーの不安定だけど確かな友情というのが、読者の胸をしめつけてきます。
- ネタバレ感想を表示
-
実はとくに重要なシーン、老犬の臭いに迷惑していた労働者が犬を射殺する場面。周囲の労働者は飼い主の老人に気を遣う素振りを見せますが、どうしようもない状況でした。銃を持って犬を連れだしてから、だいぶ間が経ってから銃声が響くのですが、明記されていないが犬は安楽死ではなく殴られたりしながら最期のとどめに撃たれています。
老人は後に「あのイヌは自分で撃てばよかった、よそのやつに撃たせるんじゃなかった」とぼやくのが印象的。
あまり言及すると最後のネタバレになってしまうけど、この撃たれた老犬はレニーの暗喩で、レニーが引き起こす事件の顛末に非常に重要な意味を持たせていました。私はこの構成の素晴らしさこそ本作最大の評価だと思います。

小学6年生の女の子ふうちゃんを中心に、彼女の父親がうつ病になったことから様々な人の優しさや悲しみに触れていきます。
お父さんの病気には沖縄のことが関係しているのではないかと確信すると、沖縄戦争当時の写真や資料を友人に見せてもらいます。その惨状は見るに耐えられないショックでした。
しかし周囲の人から沖縄に関する部分に触れると、どうしても相手の辛い部分に触れてしまうことに気がつきます。沖縄を知って相手を知りたいのに、そのせいで相手を苦しめてしまうことに悩みました。なぜこんなにも沖縄と悲しみが結びついているのか。

過ぎ去った歴史は私たちに無関係のように思えるけど、実のところ細く長い同じ線上にあって、歴史というその線の先頭にいるのだということを教えてもらったようです。
あたりまえのようになってしまっている沖縄の現実に、改めて目を向けてみると実は知らないことばかりだったり。私たちの周りには知っておくべきだけど、意識にものぼらない知らないことがあふれているのかもしれません。そして知ろうとしたならば、そこに足を踏み入れるのが憚られるような現実を目の当たりにするかもしれない。
ふうちゃんと一緒に真剣に生きて、知るべきことと向き合う勇気をもらうような、そんな気持ちにさせられました。
- ネタバレ感想を表示
-
この本を読んでいて非常に感動はしたのは2つの場面。
一つは、ふうちゃんの友達が担任の先生に宛てた手紙の内容。小学生とは思えないほどの真剣さで、正直で、力強い筆致の手紙。中身は子供らしく真っ直ぐな想いが書かれていますが、その気持が綺麗に整理されており、きちんと自分の考えを表現しています。それが結果的に担任の先生を突き動かし、ふうちゃんを感心させる出来事となっていました。
二つ目は沖縄の少年の手術が済み、連日病室で警察の事情聴取がされているとき。その日はふうちゃんと叔父さんが同室しており、沖縄の少年を問い詰めようとする警察に叔父さんが割って入ります。「法の前に沖縄もくそもない。みんな平等だ!」と息巻いた警察を前に、冷静に淡々と平等の本質を説く叔父さん。その人間味ある諭しかたに、何度読んでも涙が出てきます。不平等な過去の現実を語る叔父さんを前に、真剣な眼差しで一言一句もらさずに受け止めようとするふうちゃんの姿勢にも心を打たれます。
時代背景は沖縄戦争から30年後の1975年頃、舞台のモデルは川崎造船所の正門に至るまでの界隈ですが、おきなわ亭「てだのふぁ」のモデルはなさそう。
【猫(まやー)ユンタ】
歌の中に猫の鳴き声のおはやしが入る沖縄民謡のひとつ。ふうちゃんのおとうさんの故郷、八重山の歌です。意味は先島諸島にだけ課せられた人頭税に対するうらみつらみを猫に例えています。

【白い曼殊沙華(彼岸花)】
正式にはシロバナマンジュシャゲと呼び、原種の赤い彼岸花と黄色の鍾馗水仙(ショウキズイセン)を交配したものが、白い彼岸花となります。赤とは対象的に繁殖力が弱いので非常に珍しい。
赤い彼岸花は死を連想するイメージがついてますが、白い彼岸花は本作では幸運の象徴としてふうちゃんに喜ばれました。物語の最終盤におかあさんが「おとうさんの中に死んだ人がたくさん生きている、だからおとうさんは地球に住んでいる人の中で一番やさしい」と言う場面。神戸の丘の上の赤い彼岸花の群生の中に、たった一輪咲いた白い彼岸花は、暗におとうさんのことを示しているように思われました。

ランゲルハンス島の午後
刊行 1990年10月29日
おすすめ:
- レストランの読書
- 女子高生の遅刻について
- 猫の謎
- 八月のクリスマス
など、全25編のエッセイ。

本書から個人的に気に入ったエッセイを一つ紹介します。
タクシー料金を払う際に万札しかなく小銭がないときどうするか。禁煙しているのでタバコを買うわけにもいかず、そんなときは決まって化粧品店でシェービング・クリームを買ってお金を崩します。
それを持ったまま街を歩いていると、街がいつもとは違ったように見える。拳銃をポケットにつっこんで街を歩くかのように。いつもと違う状況が、いつもと違う景色を映し出して、それがなんだかシュールに思えるのです。
外国に行くと必ずその土地のスーパーでシェービングクリームを買う。国ごとに特色があるのか、シェービングクリームによって外国に来た実感を得られるようです。お気に入りはジレットの「トロピカル・ココナッツ」で、これを使うと一歩外はすぐにワイキキ・ビーチという気分になれます。

村上春樹の小説を読んでいると、クールでニヒルな人物が多いように思います。だから作者自身もそうなのかと勝手にイメージを重ねようとしてしまいますが、エッセイを読んでいると意外とユーモアのある人なんですね。
文章も小説とはまた違った味で、それでいて「あ、やっぱり村上春樹だな」と思えます。
そして安西水丸のイラストがかわいらしい。カラフルな色づかいだけど、ちかちかしていないマットな質感の色味、ポップさと落ち着きを両立したような素敵な絵でした。
クラッシィという雑誌に2年間にわたり掲載したエッセイ+書下ろし「ランゲルハンス島の午後」を加えて書籍化したものです。

むらさきのスカートの女
刊行 2019年6月7日
おすすめ:
肉屋のショーケースにタックルして破壊。デートを尾行した居酒屋で無銭飲食。上司の高級サングラスをパクる。
はちゃめちゃな女の狂気的な独白譚。

語り手である私、通称「黄色いカーディガンの女」が、執拗に「むらさきのスカートの女」を観察して、徹底して一人称視点で進行する物語。
むらさきのスカートの女の容姿の子細から、職歴、住んでる場所、日々の習慣まですべて把握している私。その目的はただ彼女と友達になりたいから。私はむらさきのスカートの女が、自分と同じ職場で働くようにどうにか仕向けていきます。
どうにか彼女を同じ職場に導いた私は、それからもずっと観察を続けていきます。女社会の職場、不倫、そしてむらさきのスカートの女の変化…。次第に孤立していく彼女を今日も私は観察を続けていく。

初めて読む作家でしたが、期待以上の面白さ、純文学よりもエンタメ寄りな感じで楽しめました。客観的な描写や語りがなく、主人公の一人称視点で話し言葉のように進むので、文章が読みやすいかと思います。そして終始漂う不穏な空気が特徴的。
どこまで観察してるのか、なんでさっさと話しかけないのか、主人公は何が目的なのか?こんな風に気持ちを駆り立てながら読み進めることになるでしょう。
話は分かりやすいですし、ストーリーも不穏な展開を秘めながらも退屈なく進んでいきます。スラスラと読みやすい小説であり、ちょっと踏み込んでみると考察できる楽しみもありました。
- ネタバレ考察を表示
-
【信頼できない語り手】
この主人公、実は超嘘つきの可能性が高く、彼女の言動には多くの嘘が混じっていると断定していいでしょう。このような手法を「信頼できない語り手」と呼び、ミステリー作品で読者のミスリードを誘うためによく使われます。それを純文学に持ち込んだのが、この作品に独特の雰囲気を醸し出しているのかもしれません。
彼女が嘘つきである決定的な証拠がありました。主人公は下戸だから一切お酒を飲めないと周知させていましたが、彼女はむらさきのスカートの女のデートを尾行した際に、店でビールを3杯も飲んで食い逃げしています。このように決定的な証拠を残しつつも、主人公である語り手が信頼できない言動は多く描写されていました。
昨夜のむらさきのスカートの女が何色の何を穿いていたのか、わたしはどうしても思い出すことができなかった
150pこの言動からも、もっと言えば『むらさきのスカートの女』自体が形骸化してないかとすら思われます。客観的なむらさきのスカートの描写がないこと、ただそう呼んでいるだけでむらさきのスカートを着用してるのを観測している場面もありません。
【小説】読んだ本リスト

主人公の「私」は、家政婦組合の紹介で博士のもとへ派遣されます。博士は数論専門の元大学教師。面接で博士の義姉に求められたのは、難しいことはなくただ食事から家事までの世話。ただし博士のいる離れと母屋を行き来しないことと、トラブルは必ず離れの中で治めることが条件でした。
しかし大きな問題が一つ。それは博士は記憶がきっかり80分しかもたないこと。17年前の交通事故により記憶障害が現れ、事故以前の記憶はあるが、それ以降は常に80分しかもちません。頭の中に80分のビデオテープしかセットできず、常にそれを上書きしながら生きているイメージ。
毎日が初対面となる職場に、家政婦の息子「ルート」が加わり、奇妙な3人の温かい関係が展開していきます。

タイトルに数式とありますが、算数や数学が苦手だった人も安心してください。主人公の家政婦も数学は苦手だけど、博士の話す美しい数式にどんどんと引き込まれていき、博士を理解しようと努める家政婦がその数式を文学的に昇華してくれるようでした。
家政婦が毎日訪ねても、仕事の始まりはいつも自己紹介からのスタート。前日までに交わしていた会話の文脈は一切なくなるし、博士に出会って間もない頃は戸惑うことが多かったです。
ほかの家政婦が手に負えなくても、主人公は最大限に博士の人間性と記憶の特性の理解に努めていました。毎日がリセットされる博士だけど、それでも確実に博士と家政婦と息子の関係性が深まっているのが分かります。人間関係がいかに相手の理解に努めようとする姿勢が重要であるかが読みとれると思います。
- ネタバレ考察を表示
-
義姉(未亡人)の真意
未亡人の義姉は、家政婦が仕事の範疇を越えて博士の世話を焼いた際に、やたら過剰な反応を示しました。作中に博士と義姉の2人が仲睦まじく映る写真が発見さており、明言されてはいませんが、博士と義姉が恋仲であったことが想像できます。単純に考えれば義姉の家政婦に対する嫉妬とも捉えられるでしょう。
読者の想像にゆだねられる部分ですが、おそらく義姉は博士に余計な心労や混乱を与えないように離れと母屋でなるべく接触しないようにしていました。あるいは博士の記憶が事故以前しか保たれていないとなると、博士の中の義姉はもっと若い姿のままのはず。義姉はすでに年老いた自分の姿と博士の記憶の中の自分とでギャップを感じられたくなかったとも思われます。
そう思うとわざわざ家政婦を雇って博士の世話を任せていることにも納得できます。

中学校にあがったばかりのまいは「あそこは私に苦痛を与える場でしかないの」といって登校拒否。しばらく田舎のおばあちゃんの家、通称「西の魔女」のもとへ。
畑から野菜をとってきたり、鶏小屋の卵で朝食を食べたり、田舎の新鮮な空気と大好きなおばあちゃんのもとで豊かな暮らしが始まります。
しかしまいの心をかき乱す近所の傲慢な男が現れ、鶏を犬に殺される事件も発生。不穏な気持ちを静めて、外からの刺激に動揺しないための魔女修行が始まるのでした。

にんにくをバラの間に植えておくと、バラに虫がつきにくくなるし香りもよくなる。クサノオウは猛毒だけど、眼病に効く薬にもなる。こんな植物豆知識が読んでいて楽しい、緑豊かでどこかほっとさせる物語です。
まいの母の発言「昔から扱いにくい子だった、生きていきにくいタイプの子よね」まいはそれをいつまでも覚えています。
嫌なこと一つあると、その日のすべて何もかもが台無しにされたような気分。それこそ読む人の感受性によって、どれだけまいに同情できるかが変わってきます。私もそういった経験や感情はこれまでに幾度となく向き合ってきました。
上手な人付き合い、負担にならない感じ取り方。そんな人間の心の難しさを、まいの繊細な感受性を通して読者に伝えているようでした。
- ネタバレ感想を表示
-
実はゲンジさん(近所の粗野な男)は本当に嫌な人だったのか、という疑いが私の考察する彼の人間像です。雨が続いたあとの日にスコップでタケノコを掘っていたのは嘘で、まいの死んだおじいさんのために銀龍草を探していたのではなかろうか。ゲンジさんの豪胆で遠慮のない接し方は、彼なりの歩み寄りだったのではなかろうか。
まいとは対照的な図太くて大胆な近所の男が、この小説の良さを引き立ててくれます。
【後日談】
「渡りの一日」ではまいが同級生と一日をすごす話。魔女修行で成長したまいの姿が立派に描かれています。
また、梨木果歩作品集に、ブラッキーの話(まいの母と愛犬ブラッキー)、大人になったまいが祖母を追憶する話、まいが去ったあとのおばあちゃんなどスピンオフ作品もあります。


職場の数珠屋「カナカナ堂」へ向かう途中、公園で蛇を踏んでしまい、その蛇は「踏まれたらおしまいですね」と言い、人間の姿に化けてひわ子の家の方角へ消えていきました。
部屋に帰ると昼間の蛇が50歳くらいの女に化けて夕飯を作っています。蛇はヒワ子の好きなご飯も、使うべき食器も、ビールにつぎ足されるのが嫌いなことも全て把握しているのです。
蛇にあなたは何者なのかと尋ねると「ヒワ子ちゃんのお母さんよ」と返答。心配になって本当の母である静岡の実家に電話をかけてもいつも通りのやり取りがあっただけで、母と名乗る蛇が何者なのかはわからずじまいでした。
翌日カナカナ堂に出勤するとコスガさんに蛇は追い出しなさいよと忠告されます。

主人公のヒワ子は不器用な性格で、とくに人付き合いは苦手です。前職は教師として生徒に余計な気をまわして自ら消耗して退職したこと、人の話を聞きながら食事ができないこと、コーヒーはコスガの奥さんじゃないと淹れてはいけないと思い込むところ。このどうしようもなく世渡りが下手なところが、蛇につけいれられてるようにも見えてしまいます。
不器用で周囲との付き合いが難しいヒワ子、親とも疎遠とは言わぬまでも仲が良いわけでもない。対人関係における適切な距離感をつかめないヒワ子にとって、彼女が蛇に感じた「壁を感じない親密さ」はまさに願ってもないものなのかもしれません。

理科教室の掃除を任せられた和子は準備室で怪しい人影を見ました。不審に思って正体を確認しようとすると、焦った人影はガラス容器を落として消えてしまいます。
割れたガラス容器から漏れた液体はラベンダーの香りがして、和子はその匂いを感じ取った直後に意識を失って倒れてしまいます。謎の液体の匂いをかいでから、和子の周囲で不可解なタイムスリップ現象が発生するように。
和子は自分の身に起きた不思議な現象を解明するべく、自らのタイムスリップ能力を利用してあの理科準備室の真相を探りにいきます。

この本は昔、読んだことがあったのですが、ずいぶん昔のことなので内容はほとんど忘れていました。しかし大人になって読み返しても面白かったですね。内容が分かりやすく大人から子供まで広く読み継がれるSF作品だと思います。ロングセラーとなっているのも納得。
事件の真相はすべてスッキリと解決しますし、時間軸が過去や現在を行き来しても話がシンプルなのが良い。時代背景的にも半世紀も前の作品とは思えない読みやすさです。
不本意にもこんな不思議な能力を身につけてしまった思春期の少女の動揺というのも見どころでしょう。
- ネタバレ感想を表示
-
少女がただタイムリープするだけのSF小説かと思いきや、最後まで読むと未来人、集団催眠、淡い恋愛など、この短い話の中にずいぶんとドラマチックな展開が詰めこまれています。

筋疾患先天性ミオパチーによる症候性側彎症。井沢釈華の病気で、彼女にとってはグループホームの十畳ほどの居室と、キッチン、トイレ、バスルームが現実的世界のすべてでした。
ヘルパーやケアマネなど限られた人しか関りもなく、彼女の世界はかなり限定的なものです。そんな世界を押し広げてくれるのがインターネットでした。TwitterなどのSNSを駆使して、グループホームの一室にいながらも世界とつながっている感覚です。
男性ヘルパーにTwitterアカウントがばれ、井沢釈華の性癖や歪んだ願望を含めた人間性を侮辱された彼女は、ヘルパーに対してある取引を持ち掛けました。

触れにくい話題である障害者の性を正面から扱ってるのが衝撃でした。しかも命の重み、性の在りようなどかなりセンシティブな内容です。
そして障害者である当事者視点から世間への怒りや心情吐露も印象的です。主人公の持つ身体的な歪み、ないしは歪んだ願望が社会と相容れないことを強く非難されています。
読んでいて自分を健常者として前提に立っていると、まるで責められているようで辛くなります。それだけ迫真の主張が込められているのでしょう。
- ネタバレ感想を表示
-
【ハンチバックとは】
タイトルの『ハンチバック』とは『せむし』のことで、背骨が曲がっている状態を表す差別用語です。古い小説などを読んでいると度々見かけることもありましたが、最近では聞きなれないですね。ここから主人公、井沢釈華の歪んだ願望や人物像としての歪みを表現しています。生むことはできずとも、生殖機能はあるのだから堕ろすところまでは健常な人たちのまねごとのように、その背中に追い付くことができるだろう。
井沢釈華歪みを抱えながらも、そのまっすぐな背中を渇望してるのが伺えます。

デパートの屋上から飛び降りようとしたヤスオは、決断をする瞬間にある男に呼び止められます。男は全日本ドナー・レシピエント協会の京谷と名乗りました。自ら命を断つのなら、その命(肉体)に見合った金額を受け取ってから死んだほうがいいと提案しに来たのです。
ヤスオはその提案を承諾し、精密な身体検査や既往歴などのもと、頭のてっぺんからつま先までの査定を完了させます。自らの肉体に金額をつけられると、嫌でも命の価値と平等さについて考えざるをえません。
そしてヤスオはあるレシピエントの少女と出会い、生きることを再び考えさせられるのでした。

ヤスオは自殺志願者のわりに性格は明るくふざけるタイプです。命の価値や自殺をテーマに扱う本にしては、主人公が剽軽なキャラですね。物語の重い雰囲気を和らげるバランス役ともとれますが、作風とキャラクターにギャップを生じさせてしまいます。
命の価値の議論にて、そもそも命の価値を測ることの合理性のなさに言及されます。個性や人格、その人の未来まで含めて命です。だから協会はあくまでも肉体に対して価値をつけており、自らの意志で未来を切り捨てたヤスオの命に対して論理的に測れない人格や未来は含まれないものとしました。命が数百万~数千万というと安く感じるかもしれませんが、命の抜け殻としての肉体にその機能に見合った金額しかつかないのは納得できそうな理屈です。
裏話に本作の作者が実は芸能人の水嶋ヒロで、賞金金額が高い文学賞に受賞したのも忖度がなされていたのではと八百長疑惑が上がった作品です。

コーヒーが冷めないうちに
刊行 2015年12月4日
おすすめ:
結局過去や未来に行っても何一つ現実は変わらないのだからこの席に意味はない

「学生時代に戻って青春を取り戻せたら」「社会人一年目からやり直せば」このようなタラレバにとらわれて、過去に思いをはせたことがある人は少なくないでしょう。
では特別に過去に戻れるとします。しかし過去に戻ってどんな行動を起こそうと現実は何一つ変わらないとしたら、それでも過去に戻ってみたいと思いますか。
過去に戻れる喫茶店フニクリフニクラ
舞台は過去に戻れる席があると噂の喫茶店。その席に座ると望んだとおりの時間に移動して過去にタイムスリップできますが、そこには面倒くさい、非常に面倒くさいルールがあります。

4回泣けると評判!と帯に書かれていたように、大袈裟ではなく感受性が豊かな人や涙腺が緩い人は泣いてしまうでしょうね。
過去や未来を行き来して、自分や誰かの気持ちを確かめるだけで、現実に導かれる結果がこうも変わるのかと、うまく構成されている物語でした。
現実に何かわだかまりのある人物が、過去や未来を行き来して、新たな気持ちに気づいたり、本心を伝えたりといった心温まるヒューマンドラマの連作短編集でした。

バーのマスターが趣味で作った美しいロボット「ボッコちゃん」
見た目は人間そっくりだが、できるのは簡単な受け答えと、酒を飲む動作だけ。客は新しい女の子が入ったと思うが、まともな話し相手にはなりません。ロボットなのでお酒はいくらでも飲めます。注文はたくさんいれてもらえるし、さらにロボットのタンクから回収したお酒を提供して再利用できるからマスターにとっては良い商売。
しかしボッコちゃんに本気で熱をあげる青年があらわれ、彼がお店で問題を起こします――。

1編あたり5~6ページ程度の物語が50編収録されています。本1冊あたりでは300ページを超えるものの、短く区切りがつくのでどんなに集中力がなくても読み進められるでしょう。
表題作のボッコちゃんは、たった6ページの中に流れるような展開と綺麗な落ちをつけています。話を短くまとめるためにも無駄がなく、非常に洗練された印象を受けました。星新一の1000を超える作品の中でも代表的なものであることも頷けます。
ミステリー、寓話、SF、ファンタジー、童話などバラエティにも富んでいて、飽きることなくサクサクと最後まで読み切れるでしょう。
100万分の1回のねこ
刊行 2015年7月16日
おすすめ:
まだ、わからないのか。それしかないからだよ。それだって、自分の荒野である以上、売ったら後悔するんだよ。いいかげんにわかれ。

本書から町田康の短編を紹介します。話が分かりやすく、面白みがあって、教訓もあるので、誰にとってもおすすめ。
あるギター弾きの男が、金がなく腹を空かせていました。ギターの腕は評判でしたが、人付き合いが苦手で仕事をもらえず、ずっと貧乏生活をしています。なんとか食いつないでいたが、とうとう一文無しに。家賃は滞納してるし、ギターもとうに売ってしまった。
貧窮した彼はある男にそのギターの才能を100万円で売ってしまうのでした。文字通り才能を売ってしまった彼は、ギターを買い戻してからまったく思うように弾けなくなったことに気が付き後悔します。

この短編集の趣旨は、絵本『100万回生きたねこ』と佐野洋子さんに愛をこめて。この素晴らしい絵本を礼讃するトリビュート短編集となっています。
絵本の内容を知らなくても十分楽しめますが、江國香織さんや山田詠美さんの短編は知っていた方がより楽しめるかと思います。
あらすじ紹介した町田康さんの「百万円もらった男」は、教訓たっぷりの内容で、最後の結論まで心に刺さる名言たっぷりでした。何かの才能があろうがなかろうが、これからの人生を強く生きていく勇気をもらえる話です。
- ネタバレ感想を表示
-
彼は本来自分のものであったはずの才能を、収穫する前に畑ごと売り払ってしまったようなもの。買い戻そうったって、これからも収穫のあがる畑を誰も手放すわけがありません。才能の畑をなくした彼にはもはや不毛の荒野しか残っていません。それでも種を蒔き、水をやって、一所懸命に生きていくしかないのでした。
【百万回生きたねこ】
1977年に刊行されてからずっと読み継がれているロングセラーの絵本。
王様、泥棒、孤独なおばあさん、どの飼い主も好きになれなかったトラ猫が100万回死んで100万回生きるお話です。
『100万分の1回のねこ』は、この内容を下地にしてるような話もあれば、全然関係ないけど絵本の趣旨やタイトルを絡ませているような話もありました。登場する猫はだいたいどの話においても、奔放で、自分勝手なところがあったり、気分屋なところがあったり。猫の猫らしさがそれぞれの作家によって表現されています。


偏差値48の女子大学に通う美咲、東京大学理科I類に進学したつばさ。本来なら交わることのない2人の人生が、小さなきっかけから交差していき、ある事件に進展する物語。
美咲は地元の進学校を卒業後、家族に祝福されながら女子大学に進学します。一方、つばさはエリート家庭で育ち東大に進学するも、周囲の富裕層や優秀な同級生に劣等感を抱くことがあります。
二人は大学生になってから偶然出会い、最初は恋愛のような関係が始まるかに見えました。しかし、つばさを含む東大生5人が引き起こした強制わいせつ事件により、二人の関係は加害者と被害者という最悪の形で交わることに。

結構長い本なのですが、中盤に差し掛かってようやく二人の主人公が話の中で交差します。つまり本書の前半~中盤にかけてじっくりと、人物の育ってきた背景や性格について描いているわけです。そうして人物の思想的な輪郭を丁寧に追っていくことで、どうしてこのような歪んだ事件が生まれてしまったのかを表現できていると思います。
姫野カオルコは、この小説を通じて、事件の背景にある社会的な構造や人々の無意識の差別意識を掘り下げようとしました。特に、加害者たちが持つ「自分たちは優れている」というエリート意識や、被害者が受けた不当な扱いに焦点を当てています。また、事件の詳細を忠実に再現するのではなく、フィクションという形で普遍的な問題を描くことを意図しています。
実際の事件はWikipedia等でも簡単に調べられますが、事件の概要だけを追ってもどうしてこのような結果が生まれたのか想像し難いのですね。それが小説となって人物の思想や心情の機微などが表現されることによって、よりリアルに感じられるようになります。
ジキルとハイド

ある小男と少女が十字路でぶつかった際に、小男が少女を踏みつけてその場を去った事件。小男は示談金100ポンドを支払って済ませようとしますが、その小切手がロンドンでも高名な人物ジキル博士の名で支払われたのが問題でした。
ハイドと名乗る邪悪な小男はジキル博士とどんな関係にあるのか。ジキル博士の生前遺言に、財産をすべてハイドに譲るとした内容に不信感をもった弁護士は、ジキルとハイドの真相にせまっていきます。

本編は140ページほどの中編小説。古い本にしては褪せない内容で、登場人物も少なく非常に読みやすい本でした。
ジキル博士の独白がたった140ページの4分の1も占めており、彼の切迫した思いや葛藤が鮮明に描かれています。彼の手記の中で最も印象的だったセリフに、その苦悩とこの物語の本質が凝縮されていました。
人は善人にも悪人にもなれるのだけど、そのどちらか一方になりきることができないジレンマが伝わってくるようです。
ジキルとハイドのモデルは、18世紀の高級家具職人組合長かつエディンバラ市議会議員『ウィリアム・ブロディ』です。裏ではギャンブルの種銭稼ぎに夜盗をはたらく彼は、家具師として自身で作った絞首台の初めての受刑者になりました。この皮肉な顛末までもが本作のジキルとハイドの最期に重なるところがあります。


ある朝、グレーゴルが目を覚ますと巨大な毒虫になっていました。こんな異常事態でありながら考えていたことは、外交販売員としての仕事の苦労のことでした。すでに汽車に乗る時間を逃してしまい、仕事に遅刻することが確定しています。
時間に心配した両親が起こしに来るがうまく返事ができません。相手の言語は解るが、こちらから発声して伝えることができないのです。ついに職場の支配人が訪ねてくる事態に発展し、彼は自らその姿をさらしました。
グレーゴルは虫であることに順応し、家での居場所を失い、人に傷つけられていき…最後に彼がとった選択とは――。

とにかくシュールな設定が目を引きます。しかし「虫になったこと」それ自体には意味を持たせていません。最後まで虫になった理由の説明はなく、その状況が当たり前かのように淡々と進行していきます。
こんな不条理に見舞われても、仕事のこと、家族のこと、そしてお金のことなど、彼は常に他者のためを想っていました。それが虫になってしまったばかりに、家族に気を使って怯えながら生活し、人間としての尊厳は急速に失われていきます。
仮にもし変身していない前提で状況だけを整理すると、グレーゴルは家族を養いながら嫌いな仕事を続ける重圧からノイローゼになった、とも捉えられます。虫になった設定だけを取り除けば現実にあり得る話で、まるでグレーゴルにふりかかった事故のように思えます。なぜ虫になったのかといった問いは一切なく、誰も気にせず、それこそふいに日常を襲う不条理性を描いているようです。
それでも生きていかなければならない、ここに本作の実存主義的な意図が見えます。
- ネタバレ考察を表示
-
【実存主義と不条理】
虫になったことが事故だと前述しましたが、これもまた現実に置き換えられます。例えば不慮の火災で顔を火傷して醜い姿になったとする。この容姿に対する不条理な事故という点において、虫になろうが、顔を火傷しようが、その原因や本質を追求しても仕方ない。事実は事実とただ受け入れて今を生きるしかありません。これが実存主義。
実存は存在そのもの、本質はその存在が作り上げる目的や意義だが、起きた事故に目的や意義なんてありません。
これらの解釈を広げていくと、人間というのは本質をもたずにこの世に産み落とされるものだと思えます。本は知識を与えるために書かれるし、時計は正しい時間を刻むために生産されます。人間もなにか運命や使命に定められていると思われるでしょうか。しかし人間は自分の未来を選択する能力があります。
「何のために生まれてきたのか分からない」という悩みは多いですが、本質を伴わないまま右往左往しながら生きていくから、誰もが常に不安をかかえているのです。逆に言えば何にも縛られない自由であるということ。
人生において常につきまとう不安から逃れるために目的や意味を求めるのではなく、自身の自由な意志と選択をもってして主体的に生きるのです。当然その自由には責任も伴うが、だから生きるのは楽しい。そう哲学者のサルトルは言っています。
この実存主義的な思想で、不条理に抵抗していくさまを文学に落とし込んだのがカフカの変身です。

主人公は医師のリウーと、彼の友人でありペストによる災禍で彼の仕事を手伝い続けたタルーの二人。タルーはこの本の語り手によるペストに関する重要な記録とは別に、街や日常の些末なことを手帳に記録。この手帳からも語り手の補足として引き合いに出されます。
リウーは診療室の外で鼠の死体につまづく。翌日以降も大量発生。
診療所の門番がペストに罹患。市の鼠害対策課による収集が開始。翌週には最大ピークで8000匹以上が収集された。
鼠の死体の増加が止んだが、門番がペストの症状に苦しみ死亡。
町中でペストの罹患者が増加して町はロックダウンされる。同じロックダウン状況下でも、人それぞれの営みと向き合い方が映し出されています。

語り手は終盤まで正体を伏せられていますが、語り手の記録によって人々が不条理に向き合う様相、語り手自身が不条理に見舞われる始末を見届けることになります。
この記録的な文章がいかにも客観的かつ無感動に徹しているようですが、その簡潔な文章の影にわずかな感情や気持ちが息づいてるのが不思議な読み心地でした。逆にその特徴的な文章が、小説にしては硬く読み難い気もします。
ペストによるこの不条理な世界を後世に残すための学術的記録のような重みもありながら、不条理に対する抵抗や受容のしかたが個人的な事象として捉えられる日記ともいえるでしょうか。文学的修練に培われたカミュの文体の魅力ですね。
- ネタバレ感想を表示
-
【ランベールの成長】
個人的には新聞記者のランベールが次第に心変わりしていく様子が好きでした。町からの逃走便宜をリウーに断られてからいろいろと奔走したが、合法的には抜け出せないことを悟って、密輸業者を介して衛兵を買収して脱出を試みるも失敗。最終的に彼も保険隊に志願し、自分一人の幸福よりも全体の幸福を願う人間に成長していきました。
町の惨状を目の当たりにして関わった以上、自分はもう町とは無関係の人間ではないこと。そんな気持ちを無視してパリに帰れば、待っている彼女に顔向けできなくなるだろうと想像します。
最初は器の小さい嫌味な人間だと思っていたけど、いざ自分が同じ立場になってみたら、やっぱり自分も我先にと町から出ようとするかもしれないです。だからこそ彼の人間味にはリアリティがあって、その成長ぶりに希望を感じられるのです。
ペストの舞台となったオランは、アルジェリアの主要な港町で商業の中心地です。当時はフランスの植民地だったので、本土にお金を流すための経済優先の町という感じ。ロックダウンされて経済がストップすると何もない町なので、登場人物たちは一層不安に駆られています。

作者のカミュは不条理哲学を打ち出した人で、戦争・災害・全体主義といった極限状態への抵抗を描いてきました。本作のペストはナチスドイツに対する暗喩ともされています。原作の1947年は第2次世界大戦が終わって間もないので、多くのヨーロッパ人はこの本を自分事のように理解していました。


老人サンチアゴはかつて優秀な漁師だったが、現在は年老いてずっと不漁続きとなっていました。今回が最後の漁になる覚悟で出港して、長年の習慣から手堅く仕掛けを準備して獲物がかかるのを待ち続けます。
ついに鉤に巨大なカジキがかかり、老体一人で3日間の孤独な奮闘が繰り広げられていきます。孤独な老人の精神の支えになっていたのが、彼を慕ってくれていた少年マノーリンの存在でした。
しかし老人にはその後さらなる試練が待ち受けているのでした。

老人は今回の漁以前は三か月近く全くの不漁だったので、周囲からはもう落ち目だとされていました。そんな状況で、老人が漁師としてのプライドを携えて、慕ってくれる少年のために最期にひと花咲かせる話。
状況自体は船上で水中のカジキとひたすら膠着状態、場面転換がなく老人のモノローグが続くので、少々退屈で読みつかれる気もします。また、老人は決して嘆いたり、状況を悲観したりはしません。サンチアゴの海に対する敬愛が彼を支えてくれたいたのでしょう。
読み手の感動を誘うような湿っぽい感じではなく、静かに感動させるドライな読みごたえでした。これがいわゆるハードボイルドといわれる感覚なのかもしれません。

人生に疲れた40歳の作家ファウストは、パートナーと別れ、長年暮らしたミラノを離れてフォンターナ・フレッダにやって来ます。
レストランでコックの職を得たファウストは、そこで知り合ったウェイトレスのシルヴィアと付き合うように。レストランオーナーのバベットや、元森林警備隊のサントルソらとも交流を深めていきました。
やがて狼たちがイタリアンアルプスからおりてきたころ、シルヴィアから「富嶽三十六景」の画集を贈られ、冬は仕事がないので別々の道を行くことに。
人の山に対する考え方は、そこに暮らす人と、遠ざかっている時ではずいぶんと異なるもの。遠くで考えると山の現実はぼんやりとした抽象的な概念になり果ててしまいます。北斎の絵の奥に小さく描かれた富士山が、てっぺんに雪をかぶったただの三角形になってしまうように。

葛飾北斎が物語のモチーフ、小道具として重要な役割を果たしています。今この瞬間を生きる人々の暮らしぶりと、そんな人間たちに無関心な泰然自若としていつもそこにある山とのコントラストを描いているようでした。
それほど長い本でもなく200ページちょっとを36章に細切れにしているので、サクサクと読み進めやすいです。読み終わった後も、それぞれの章をかいつまんでショートのように読めるのが魅力的な本でした。
舞台となる山の話がメインなので、登山経験などがあるとより想像しやすいですね。アルプスで1000m登ることは北に1000㎞移動することに近しいという話。標高が上がることで気候や植生が変わるのですが、フォンターナ・フレッダが1815mでそれを北移動に換算するとデンマークやノルウェーに相当します。北極点なら5000㎞弱だからモンブランの頂上といったところ。山登りがはるか遠くへの旅に類似した経験を得られる新たな視点の魅力でした。
- ネタバレ感想を表示
-
【ファウストの魅力】
フォンターナ・フレッダで得た教訓は「食事の支度をする人間は常に必要とされているが、書き手の需要は高くない」作家としてうだつの上がらないファウストですが、彼には人間的な魅力があって、まず山に移住してあっさりと仕事をみつけたこと。そして出会う人それぞれ、うまく関係を手繰り寄せて山での暮らしに溶け込んでいったこと。
彼の作家業が大成するかは分からないけど、ここでの暮らしが幸せなものになっていくような予感は感じられました。
そしてなぜタイトルが「狼の幸せ」なのか。木々は動物とは異なり幸せを求めてどこかに行くことができないので、種が落ちた場所で咲くしかありません。
しかし不思議なのは狼で、なぜか落ち着かず移動を繰り返して不可解な本能に従って動きます。どこかで獲物があふれていても何かが定住を妨げせっかくの恵みを放り出し、常に新天地を求めています。雌のにおいを追い、群れの遠吠えを追い、明確な目的もなかったりもして。
ファウストはそんな狼だったようです。ファウストに限らずシルヴィアも、バベット、サントルソも。どこかで合理的な判断とはかけ離れた選択のもと、狼のようにフォンターナ・フレッダに辿り着き、また別の世界に移っていくのかもしれません。
作者(パオロ・コニェッティ)自身、作家として行き詰り、この実在するレストランで2年ほどコックとして働いた実体験が反映された物語。


舞台は水の都イタリアのヴェニス(ヴェネツィア)とベルモント(架空の都市)における、貿易商(アントーニオー)と金貸業(シャイロック)の2人を巡る物語。
貿易商のアントーニオーは親友から結婚費用を貸してほしいと頼まれるが、彼の財産のほとんどは航海中の船にあって貸せるだけの金はありません。親友の頼みとあらば、強欲で高利貸しといわれるユダヤ人、シャイロックに頼るほかありませんでした。
シャイロックがアントーニオーに提示した条件は、実質命と引き換えの契約でしたがアントーニオーは承諾します。しかし彼の貿易船が難破したと連絡が入り、金を返すあてがなくなってきたのです。

古い作品なので時代背景や設定を知っておいたほうがより理解も深まるでしょう。まずこの当時におけるユダヤ人の立場を明確にします。
作中舞台はイタリアですがシェイクスピアはイギリスの作家です。イギリスではユダヤ人は排斥対象とされており、実はシェイクスピア自身もユダヤ人を知らずにイメージだけでここまでのユダヤ排斥を作品に落とし込んだのではと言われています。
つまり作中のキリスト教徒であるアントーニオーにとってシャイロックは忌避すべき対象で、シャイロックにとってはキリスト教徒であり商売の邪魔をしてくるアントーニオーは目の敵だったわけです。
キリスト教では利子をとることがよくないこととされており、そのために金貸業で栄えたユダヤ人はイギリス人の反感を買い、迫害された後に国から追放され、イギリスからユダヤ人が姿を消す数百年の空白期間がありました。ただしユダヤ人は進んで金貸業を選んでいたのではなく、仕事がそれしかなかったという状況からの結果です。

【エッセイ】読んだ本リスト

哲学というと固いものに思われますが、いわば久保さんの狩猟に対する思いの変遷を辿ったエッセイ調の自伝です。久保さんは日本の狩猟業界では知らぬ人がいないであろう伝説のハンターとなっています。それは彼の獲物に対する誠実さと、ハンターとしての矜持が備わっているからでしょう。
父の影響で幼少期からサバイバルを経験し、大学に進学すると銃の所持許可を得て父から村田銃(ライフル)を譲り受ける。
標津町で羆による被害が多発していたため、移住して標津をホームグラウンドに。優秀な猟犬と共に、単独猟を極めることを決意。
日本でハンターとして生計が立ち、次なる目標は本場アメリカで腕試し。アウトフィッターズ・アンド・ガイズ・スクールをトップの成績で卒業。
離農した牧場を引継ぎ、家庭を持って、その後もハンターとしての活動は継続していました。アメリカのハンタースクールの日本法人も立ち上げました。※2024年4月10日 76歳で逝去。

エッセイ調なので平易な文章で分かりやすい内容です。久保さんの性格から淡々とした調子ですが、ときに感情の高ぶりをみせる熱のこもった文章になっていてメリハリがあります。時系列に沿って書かれているのも読みやすいポイント。
幼少の頃に猟の魅力にとりつかれて、大学卒業してからプロとして単独猟を極め、最高の猟犬を育てあげ、渡米して本場のハンターの世界で活躍し、帰国してからホームグラウンドの標津に根を下ろします。数々の苦労はありましたが、結果だけ見てみると常に向上心を持って順風満帆に駆け上がっていったイメージでした。
食事シーンを描写するのも上手で、獲ったばかりの羆やシカの心臓を焚火にあぶって、焼けたところからナイフで削いで食べるのはハンターの特権です。シカ肉の刺身、川で獲った魚を混ぜ込んで飯盒で炊いたご飯など、どれも美味しそう。味の表現が優れた料理エッセイとはまた違った、自然の中で命のやりとりをした状況から生み出された食の見せ方がそうさせてるのかもしれません。
相棒の猟犬はアイヌ語で火の女神を意味する「アペ・フチ・カムイ」から。この本の表紙イラストになっています。


本書のエッセイから1編紹介します。
大学1年生の上京したてのお上りさんだった著者は、カットモデルを探しているという友人の言葉に飛びつきました。しかし美容師の上司がチェックしていること、ストップウォッチで時間を図る人や、なにやらメモを取る人など、現場の空気はピリピリしていました。
カットが終わってチェックするとき。上司の一言「バランス考えた?この子顔のフォルム長めでしょう」 さらに「後頭部に欠損あるじゃんか」と追い打ち。上司が美容師に指摘するたびに、面長や部分ハゲなど、モデルとなっている自分のネガティブポイントがどんどん掘り起こされていきます。
無料カットや東京クオリティの技術を受けられるおいしい話だと飛びつくのは甘かった。プロ試験を控えた美容師のカットモデルをするということは相応の覚悟も必要なのです。

浅井リョウの二十歳前後のできごとを綴ったエッセイ集。年代的にゆとり世代にあたる著者の赤裸々な話です。構成は主に学生時代のエッセイが20篇。元は「学生時代にやらなくてもいい20のこと」の単行本があり、これに社会人となってからのエッセイを3篇追加し、改題して筒井康隆の「時をかける少女」のパロディタイトル「時をかけるゆとり」となっています。
朝井リョウさんの本はいくつか読んだことありましたが、このエッセイを読むと作者の印象が大きく変わりました。若くして大きな文学賞を受賞した経歴や、作風からも、なんとなくクールでニヒルな印象を抱いていました。実はとてもユーモアあふれる楽しいかたなんですね。
そして朝井リョウさんならではの特徴ですが、よく観察あるいは記録された文章が綴られています。普通に過ごしていたら見過ごしてしまうような日常の発見や面白さをしっかりとすくいだして、面白おかしく文章として成立させる筆力がプロ作家そのものです。さらに作家は書くだけではありません。多くの人生経験が作品に奥行きをもたらすのでしょうが、彼にもとにかく経験をしようという貪欲さが表れているようでした。
ツチノコ撮影日誌
刊行 2024年6月15日
おすすめ:
いま映画学校で「映像民俗学」を教えているのですが、民族に関する記録映画を民俗「学」と学にしていいのかどうか疑問がありますね。「学」としてしまうとその時点で型というか形式ができてしまう。民俗や習俗を記録するというのは、そうした型がないのではないかと思うんです。

ツチノコの歴史は古く縄文時代から生息したといわれています。岐阜県高山市の飛弾民族考古館には6000年前のツチノコ形の縄文石器が確認されています現代のツチノコの目撃情報や生息地での民家のインタビューなどを記録した映画製作話です。
本書ではツチノコに似ている生物にヤマナメクジとアオジタトカゲが紹介されています。個人的にはアオジタトカゲの手足が隠れていれば想像のツチノコにそっくりなので、ペットで逃げ出したツチノコを見間違えた説が濃厚だと思っています。
また著者である今井監督の自伝も並行して、どうしてツチノコを題材にした映画を撮るのか、それらの背景をベースに自分がどのようにしてドキュメンタリー映画監督への道を歩んできたか、そしてどんな作品を撮ってきたかの話が語られていました。

東白川村では30年以上にわたって毎年ツチノコ捜索イベント「つちのこフェスタ」を開催しています。これを実在しない架空の生物を追うくだらない催しととるか、ツチノコにロマンを求めて楽しむ恒例行事ととるか。参加者の多くは名古屋から来てることもあり、普段自然に触れない人たちの息抜きやリフレッシュのようなものが本質でしょう。私もつちのこフェスタに行ってきましたが、子供から大人まで楽しめる非常に良いイベントだと思いました。
岐阜県以外、全国各地でツチノコの伝承があって捜索イベントや催しが行われてきましたが、結局つちのこに対する熱量を維持できずに下火になっていくのが多いようです。東白川村がすごいところは村を上げて、それが数十年続いているということ。さらに村の名産品である檜とお茶もしっかりPRしています。
伝説となる物語には終わりがあってめでたしとなりますが、ツチノコの物語には終わりがなくそれが魅力になっているのかもしれません。
【ビジネス・実用】読んだ本リスト

PDCAの計画において慎重さと大胆さのバランスが肝要で、その時点で可能な限り精度の高い仮説を立てる必要があります。とくに計画段階が非常に重要なようです。
- KGI(Key Goal Indicator)の設定
- 期日を決めて目標を定量化
- 現状とギャップの洗い出し
- ギャップを埋める課題を考える
- 課題に優先度を与えて3つに絞る
- 各課題のKPI(Key Performance Indicator)の設定
- KPIを達成する解決案を考える
- 解決案に優先度を与える
- KPIを掲示したり計画を可視化して、計画を強く意識付けすると効果的。
計画から導き出したKPIを業務フローに落とし込み確実にやり遂げる行動力、これまでの正しい計画と実行の上に成り立つ振り返り、これらを短期スパンで繰り返しながら最終的に長期目標を達成します。

『優先順位』という言葉が多用されており、とくにIT業界の開発用語『アイスボックス』をToDoにも応用し、いつかやるけど今やることではないものをタグ付けして管理しています。先送りすることは悪いことではなく、タスクを可視化して留保する手段として活用しています。
それぞれのマネジメント段階で補足も添えられており、解りやすく丁寧なハウトゥー本だと思いました。PDCAサイクルを実際に回していく説明に並行して、英会話修得やダイエットなど実例を交えているのも理解の助けになります。
PDCAそのものはシンプルなフレームワークで、必要とするツールも最低限で済むが、シンプルゆえに適切な運用をしないと効果が十分に検証されてないことが分かりました。
すごい左利き
刊行 2021年9月29日
おすすめ:
「左利き」は天才? それとも…変人?

右利き優位の左脳は言葉や計算、論理的思考、による直列思考が得意。対して左利き優位の右脳は様々な情報が同様に浮かぶ並列思考の脳です。
左利きの人が左脳を鍛えるにはToDoリスト作成、日記をつける、ラジオを聴く、ブログやSNSで発信するといった言語化につながる活動が有効です。中でも外国語の勉強は脳番地をフル活用して左脳を成長させる最も効果的な方法です。単語の意味を覚えるために記憶系、感情系、思考系で文章をつくり、運動系を用いて書いたり話したり、伝えたいことを整理するために伝達系も活用します。
多くの左利きの人はこれまでの人生経験からも、両方の脳を活用しやすいという大きなアドバンテージを有しています。初めは不自由に感じるかもしれませんが、その不自由さから創意工夫をこらして積極的に右利きとなることで、最強の左利きになれるとされていました。

私自身も左利きでありながら、ツールによっては両利きのものがあるので、本書に書かれている両脳活用の希望の兆しは想像できます。積極的に右手(左脳)を使って両利きを目指すのは、脳科学的な観点から優秀な思考力を得るための新たなアプローチかもしれません。
実際には忙しい多くの現代人が、思考力という目に見えない成果の為に、両利きを目指そうなんてばかげたことは実践しないと思います。しかし右利き優先デザインの世の中で、左利きの人が強いられてきた小さな苦労は、両脳を刺激して優秀な脳の使い方をしてきたかもしれないという、自己理解を深めるきっかけにはなったかもしれません。
13歳からの地政学
刊行 2022年2月25日
おすすめ:
かなりの外交の専門家が読んでも読み応えのある内容を、極めてわかりやすく書いている。若者だけでなく、すべての世代の必読書だ。

アンティークショップの貿易商である「カイゾク」が、二人の少年と少女に7日間の講義形式で地政学を教える物語仕立ての入門書です。その中から2つ、超要約して紹介します。
【物も情報も海を通る】
貿易の9割は海を通って実現しています。空輸も活用されているのかと思いきや、圧倒的にコスト面で海路が利用されています。また海底ケーブルは情報の要。さらに海の深さにも着目すると日本の海水体積は世界トップクラスであり、経済的にも優位な点があります。地政学においてまずは『海』の重要性をおさえなければなりません。
【絶対に豊かにならない国々】
なぜアフリカにお金がないのか。気候や食糧問題ばかり取り沙汰されるが、実は天然資源が豊富で、サハラ砂漠は大陸の1/3以下で緑や水も豊か。住みやすい土地も多い。理由は端的にいって政治家が海外に金を流してるからです。アフリカが大国の植民地支配の歴史にあり、ヨーロッパやアメリカがそのお金を吸い上げている。そんな構造は現代でも変わらず、アフリカの上層と外国がタッグを組んでいるのです。

私たちは学校の社会の授業で地理や歴史については学んできました。そして政治は公民という科目で勉強してきました。そこに地政学という観点を得ると、過去に学んだ地理や歴史のポイントが線となって繋がるところが生まれるのです。
国際政治に関するニュースを見ていても、地政学的な視点があるかどうかで捉え方も変わってくるでしょう。
タイトルには「13歳からの~」とありますが、本書は大人が読んでも役立ち、楽しめる一冊だと思います。
サクッとわかるビジネス教養地政学
刊行 2020年6月13日
おすすめ:
地政学を戦略に活用すれば「道」や「要所」をおさえてエリアを支配するのが効率的でしょう。
国の存続に物流は欠かせないものとなっており、地理条件から経路が限られている要所をおさえるのが戦略です。

地政学は地理的な条件をもとに、他国との関係性や国際社会での行動を考えるアプローチ。本書では特にアジア(中国VSアメリカ)、中東(イランVSアメリカ)、ヨーロッパ(EU・NATO VSロシア)の地理的な衝突から国のふるまいをマクロな視点で言及しています。
日本との関係国における情勢も気になるトピックが複数。なぜ北方領土問題が解決されないのか、沖縄米軍基地がいかに優れた拠点かといった解説がされています。

アメリカと中国の関係、沖縄基地や北方領土の問題、中国の一帯一路、イギリスのEU離脱、香港デモなど、世界情勢の「なぜ」がよく分かる一冊です。カラー図解が豊富で、タイトル通りサクッと読み進めるのにちょうど良いですね。
国際問題には宗教、民族問題、人種、歴史的対立などあって、地政学ではあくまでも地理を前提に、ビジュアライゼーションの概念で紐解いていきます。また、戦争における戦略概念には上位から順に世界観、政策、大戦略、軍事戦略、作戦、戦術、技術という階層があり、その中の上から3番目にあたる大戦略が地政学的観点です。
地政学に義理人情や好意など一切なく、国益第一の領土や権力争いで殺伐とした話になりがちです。こうしてみると世界平和なんて耳障りの良い言葉も、それぞれの世界観、国、人、民族、宗教によって、そもそもどのような状態が平和なのかが異なります。人びとが自分たちに都合の良い平和を求めるからこそ絶えず争いがおこり、平和を求めることこそまた争いの種になっているのが皮肉な哀しい話です。
人生・仕事の結果が変わる 考え方
刊行 2017年3月23日
おすすめ:
利他は社会をよりよい方向に導く心。犠牲を払ってでも世のため人のために尽くすことは、実は自分自身の人生も好転させます。

ビジネスの世界では挑戦的で独創的なことをしようとするときに必ず多くの障害が出てきます。これを克服するには一途な信念で乗り越えるしかありません。
1984年電気通信事業の自由化により国策会社の電電公社が民営化されNTTになり、通信事業への新規参入が認められました。しかし明治以来のNTTによる膨大な通信インフラに誰も太刀打ちできません。
しかし国内の長距離電話料金が世界的に見て高すぎるため、通話料金を安くする大義を掲げて不利な局面を駆け抜け、現在では市場をリードするKDDIとなりました。

稲盛和夫という松下幸之助に並ぶ経営の神様による言葉の数々。その功績と人格からこれ以上ない説得力を含んだ一冊です。
特筆すべき点は、人間の「心」や「正しさ」に訴えかける内容が多く、経営者のみならずすべての人に通ずる誠の言葉にあふれています。難しいことは一つもないのだけど、いざ改めて考えてみると自身を見直さなければいけないことに気づかされます。
善い考え方が人を育み、周囲を奮い立たせ、社会に影響を及ぼす。そんな原点に立ち返るための「考え方」を問われているようです。
自分のアタマで考えよう
刊行 2011年10月28日
おすすめ:
プロ野球の将来性
結論が出ない会議の秘密
少子化問題のゆくすえ
婚活女子の判断基準
消費者庁が生まれた真相
就活で失敗しない方法
自殺の最大の原因
電気代の減らし方
NHK、BBC、CNNの違い

会議に結論が出なくてずるずると長引くことがよくあります。何かを決めるときには「情報」とは別に「意思決定プロセス」が必要なのです。
例えば買い物において価格情報をひたすら収集するのではなく、上限の値段を設定してフィルタリングすること。なんとなく夕食を考えながらスーパーへ行くより、メニューとレシピを決めてから買うべきものをリストアップすれば時間もお金も無駄がありません。
意思決定においては今求められている情報に集中することが大切で、最初に考えておくべき決めるプロセスというものがあるのです。
思考は情報収集作業ではなく、インプットした情報をアウトプットして結論に導く変換プロセスです。仮の結論でも間違っていても、なんらかの結論にたどり着くべきでしょう。

2005年から自分の思考をブログに書きしたためている、社会派ブロガーちきりん氏による著書。TwitterやVoicyでよく見ますが、とても参考になる話や的を射た意見が多いです。SNSで影響力の大きい人にありがちな、とがった発言なども見られないような気がします。きっと長年インターネットを渡り歩いてきた、処世術のようなものがあるのでしょうね。
自分のアタマで考えた意見が常に支持されるとは限りませんが、借り物の意見やつまらない感想を述べる程度から脱却した、社会人としての品のある議論には欠かせないスキルだと思います。
テレビのニュースを見て「へ~」と頷いて次の日には内容を忘れてしまうような人に、思考力を鍛えるトレーニングとしておすすめできる一冊です。
人生、このままでいいの?
刊行 2019年3月20日
おすすめ:
質問上手は、自分上手。
わかっているようでよくわからないのが「自分」。自分の姿を見るために「鏡」が必要なように、自分の心と対話する道具が必要だ。
そのもっとも効果的なものが「質問」。

本書は11の質問によりあなた自身の力で幸福への道筋に気づかせようとしてくれます。書き込み式のノートのような構成なので、読書というよりも考えながら自分を見つめなおすワークショップだと思ったほうがいいです。
例えば本書の中から6つ目の質問「どんな自分でいたいか」
自分の性格は自分自身によって形成されてきたものです。環境が要因しているものもあるかもしれませんが、同じ環境にいる人でもそれぞれ違うように人は成長します。つまりどのように生きていくかは自分の選択によって作られるのです。
それを踏まえて自分をどんな人だと思うか、周りからどんな人だと思われたいか、自分のどこが好きで、自分のどこが嫌いか、自分らしく居られる場所はどこか、心地良いと思うのはどんな時か。
これくらい深堀りして一つの質問を突き詰めていきます。
教養としてのブランド牛
刊行 2023年8月28日
おすすめ:
35年以上にわたって和牛の肥育を生業とし、自らもブランド牛を立ち上げた著者が、生産者ならではの目線も盛り込みながら、ブランド牛にまつわる知識と魅力を幅広く語っています。

日本のブランド牛のルーツから地域ごとの特徴、海外で愛される理由、海外の牛肉との違い、日本独自の肥育方法、等級の評価基準などブランド牛にまつわる知識が得られる一冊。
世界の人をも魅了する日本独自のブランド牛、明治以降に改良が重ねられ1944年に和牛の認定が確立。著しい和牛改良の伝説スーパー種雄牛が「田尻号(1939~1954)」です。産子数1500頭近く、全体の20%の170頭が種雄牛となり、日本の和牛改良に多大な貢献をしました。2012年全国和牛登録協会の調べによると、全国の黒毛和牛の繁殖雌牛の99.9%が田尻号の子孫であることが証明されています。
和牛は世界的にも個性が際立っていて、いうまでもなく霜降りが世界の牛肉の中では稀有なもの。日本独自の改良と肥育技術によって発展してきました。さらに欧米との食文化の違いなどからも、日本の和牛ステーキは特別なものとなっています。

牛のこと、牛肉のこと、等級や牛の呼称など基本的な知識が広く解説されています。
その上で著者の自伝的な側面も交えながら、ブランド牛の成り立ちや肥育技術などちょっと踏み込んだ話まで展開されています。著者が石原牛というブランド牛を保有していることもあって、本書からのPRを感じなくもないですが、牛のプロとしての内容は参考になって説得力もあります。
日本の和牛が世界的に見ても優れた技術と品質を有しており、それを誇りに思っているのが随所に表れていました。そのブランド力を維持していくことも農家の務めであり、我々消費者にも知っておくだけで意味があると訴えかけています。
和牛と表示できるのは黒毛和種、褐毛和種、無角和種、日本短角種とこの4種間交雑種のみ。一方で国産牛に分類されるのは乳用種(主にホルスタイン)や、F1という乳用種と和牛を交配させた交雑種。
4品種あるがその98%が黒毛和種。黒毛和種はサシ(脂肪交雑)が入りやすいからです。つまり和牛=ほぼ黒毛和種といっていい。
また、日本三大和牛は神戸牛(兵庫)、松阪牛(三重)、近江牛(滋賀)、米沢牛(山口)です。近江と米沢は同列。これらは世に名前が知られてからの長い歴史があり、300以上のブランド牛の中でも群を抜いています。

等級のABCは量の判定で味に関係ありません。歩留等級と肉質等級は枝肉の第6~第7肋骨間ロース芯の切断面で判定します。部分肉歩留が標準ならB、それより良いならA、劣るならCです。一般的に和牛でBやCになるケースは少数で、9割はAランクになります。
肉質等級は「脂肪交雑」「肉の色沢」「肉の締まり及びきめ」「脂肪の色沢と質」の4項目それぞれ5~1段階で評価して、その中の最低ランクがついた項目に準じて肉質等級が決定します。つまり5等級はオール5でないとつかない評価であり、一つでも低い評価項目があるとそれに引っ張られて全体の肉質等級が低くなります。

スターティングストレングス
刊行 2019年4月5日
おすすめ:
原本が海外なので、例えば栄養に関する内容が3500~6000kcalなどとてつもないカロリーになってました。日本と欧米で基準が異なる点もあるので、その点も踏まえて読み進めていいく必要がありそうです。

5種目の主なバーベル種目に対象を限定し、それぞれを何十ページにわたって詳細に説明しています。バーベル種目は多くの筋群の動員、可動域、高重量を持ち上げるポテンシャルが高い運動です。やり方だけでなく、バイオメカニクスや解剖学の観点からの「なぜそのやり方か」までの解説を含んでいるので説得力が違います。
そもそもマシンの始まりはアーサー・ジョーンズが、ノーチラスを開発したところから。当初、身体をハードに鍛えるにはバーベルの扱いを覚えるしかなかったため、革命的でビジネス的にも大成功しました。ジムにとってもスタッフ教育のコストが大幅に削減されます。
しかしマシンサーキットはとても効率が悪く、ある人がバーベルに切り替えてから1週間で、12台のマシンで鍛えた何ケ月もの期間全体で増えた体重以上の増加もあったという話もあるほどです。人体は全体がひとつのシステムとして機能するものであり、マシンによって部位ごとに分割して鍛えるのは道理にかなっていません。なぜならマシントレーニングで得られた筋肉を、日常動作で同様の使い方をすることがないからです。

専門性の高さから値段が高い…。定価5,800円(税抜)なので、大学の参考書としても使われるレベルですね。そのぶん内容が充実していて、バーベル種目の正しい知識を入れるならこの本一択だと思います。
筋トレ本は数多くありますが、1つの種目を見開き1ページ程度の浅い内容ですませる本が多いこと。サイドレイズやレッグエクステンションのような、単関節運動なら簡単に理解できるかもしれませんが、スクワットやデッドリフトのように複雑な多関節運動で且つフリーウェイトについては、見開き1ページ程度の短い説明では適切なやり方は身につきません。むしろ怪我などのリスクにもつながります。
全体的に専門性の高さと、一つの内容に対する深さからトレーナー向けの本だと感じます。ある程度トレーニングの知識と経験がある人が、さらに深い理解を得るのにも最適です。
孤独の愉しみ方
刊行 2010年9月1日
おすすめ:
心の賛沢は、一人の時間から
孤独には、力がある。

本書は「孤独」をテーマにした5章立ての名言集となっており、名言に続いて解説や出典となる本の文脈が記載されているアンソロジー形式です。
- 孤独が一番の贅沢
- 簡素に生きる大切さ
- 心を豊かにする働き方
- 持たない喜び
- 自然の教え
本書の中から個人的に特に気に入ってる内容を抜粋して紹介します。
「みんな」という言葉にまどわされてはならない。「みんな」はどこにも存在しないし、「みんな」は決して何もしてくれない。
多数による同調圧力をもってして相手を丸め込んだり、「みんな」という主語の大きい曖昧な対象に責任をおしつけたり、そうやって本来の自分を喪ってはいけないと教えてくれます。

孤独が決して悪いものではないことや、むしろ人間が本質的に豊かな精神性を育むためには孤独が必要であることが分かります。
自分が一人であることに寂しさを感じているのであれば、それは孤独を味方にして自分を成長させるチャンスでもあるのです。
道草を食む
刊行 2023年10月20日
おすすめ:
なんとも可愛くて、賢くて、意外とおいしい 道草の世界へようこそ

春夏秋冬の四季を通して楽しめる雑草21種を、その食べ方から生態や文化などの観点からスポットを当てる雑草マニアの本。植物に通じていなくても楽しく読める内容となっています。
ポッドキャストで人気番組となり書籍発売に至った稀有な例。私も楽しみに聞いており、中でも特に身近で分かりやすいお気に入りのエピソードがヨモギの回でした。
ヨモギの新芽は本来春だが、人里近い場所で何度も刈り込まれて再び新芽を出すものは通年入手可能。Michikusaさんはド根性ヨモギと呼んでいるそうです。通常のヨモギより香りが強く単体では使いにくいが、強烈な香りを乳成分でマイルドにするポタージュがおすすめ。

七草をはじめ、草餅の原料となるヨモギやつくしの佃煮など、雑草は意外にも身近で、日の目を見ることのないものも活用の仕方でとても暮らしが豊かになります。そんな魅力を伝えたいという思いがこもった一冊。
雑草は山菜取りや園芸よりも手軽で、フィールドワーク的な楽しみもあるのがメリット。食べるだけでなく薬効、染料など、先人の知恵がつまった活用まであります。
雑草紹介のほかにコラムが10本掲載、丁寧な雑草レシピ、落ち着いたマット調の素敵な写真など、役立つ知識や見て楽しめる要素が満載です。
- ネタバレ感想を表示
-
個人的に一番食べてみたいのが「スベリヒユ」でした。地域によっては園芸種として栽培されているようです。肉厚でシャキッとしていて、ぬめりがあり、ほのかな酸味もあって、ダントツで食味の良い雑草だそうです。その上、植物性オメガ3脂肪酸のα-リノレン酸が豊富であったり、スーパーフードと呼ばれるほどポテンシャルのある植物なんですね。
本書の中でこれだけ覚えておけば役に立ちそうだなという一文。『手で抵抗なく折り取れる箇所』で収穫することが雑草や山菜を収穫するうえでも大切なポイント、とのこと。これに限らない植物もあるかもしれませんが、多くの食用草花に通用する知識は覚えておいて損がありません。


ただの絵本と侮るなかれ。美味しいコーヒーを求めるなら、最初の一冊におすすめのコーヒー入門本です。「美味しい」は人それぞれ違う主観的なものですが、その前提を踏まえてまず正しいコーヒーから、それぞれの「美味しい」の求め方を指南してくれます。
豆の産地や銘柄も大事ですが、まずは基本的な知識があったほうが間違いなく美味しいコーヒーが飲めます。なにより大事なことはコーヒーは自由に楽しむこと。 ブラックが一番ではなく、ミルクを入れたり、アレンジしたり。 酸味や苦みが気になるならお湯を少し足したり。「コーヒーとはこういうものである」といった固定観念や誰かの情報にとらわれると楽しめなくなってしまいます。
【漫画】読んだ本リスト
漫画 君たちはどう生きるか
刊行 2017年8月24日
おすすめ:
自分を責め立てるほど苦しみを感じているのは、正しい道に向かおうとしている証なんだ。

中学2年生のコペル君、亡くなった父は銀行の重役でそこそこの家柄。中学校の友人は実業家、大学教授、医者などの家系で、比較的上流の未来を期待される子供たちへ向けた話です。
学校や日常生活を通して、ものの見方、社会の構造、関係性を捉え、すぐれた洞察力と豊かな道徳的感性から発見を広げていきます。
そんなコペル君の発見に、叔父からのアンサーとしてノート形式で語られていきます。

コペル君の精神的な成長、友達の貧困、人間性の追求といった『より良く生きる』ための指南が凝縮された教養教育本でした。
漫画版だというのに文章量はかなり多いけど、コマ割りが大きくてさくさくと読みやすさはあります。小説版も読んでいますが、おじさんのノートの内容はそのまま小説も漫画も同一です。ストーリーは漫画でサラッと進めて、大事なことが書かれたおじさんの手紙は忠実に文章として載せています。
どう生きるべきか、ではなく、コペル君のあらゆる発見を起点にした社会的な認識のもとで、『どう生きるか』というあくまでも提示になっています。このタイトルが優れているところですね。

小学校のサッカーの練習終わり、家に帰る途中で捨て猫を拾った少年なつる。母がアレルギーのため家では飼えないと断られます。仕方なく外に出て猫を諦めようとしたところ、クラスメイトの鈴村に偶然会い、飼育費を払う条件で彼女の家に引き取ってもらうことに。
鈴村は父が置いて行った養育費でスーパーで食材の買い出しから家事まで、弟の面倒を見ながら生活のすべてをまかなっていました。未だに母に甘えているなつるは、そんな彼女の生活を見て驚きと戸惑いを露わにします。
そして彼女たちが抱えていた秘密、父が子供二人残して出ていったきりの生活、「とうふ」と名付けられた拾い猫を見守っていきます。

たった1冊で完結する短いストーリーの中に、キャラクターそれぞれの感情や想いがパラパラと小さな粒となって広がっているイメージ。それでいて物語全体がばらけずに、きっちりとまとまっているのがこの漫画の良さです。
自分が小学生の頃の不器用さや無力さが思い起こされるような感じです。非現実的な話であり、どこか現実味も帯びていて、この作品がもつ独特の魅力にからめとられました。内容としては「小学生がそんなことしないだろう」とつっこみを入れられそうなところもありますが、あながち絶対にあり得ないとも言えない状況が絶妙です。
他人にはとうてい理解できない秘密を抱えて生きていくこと、唯一の理解者がいてくれる救い、これらに想像をはせると、感情移入が止まらなくなり、私にとって特別な漫画の一冊になりました。
【サウンドドラマCD】
この漫画のファンはたくさんいて、その中で声優の小林祐介さんと種﨑敦美さんのふたりがとくに好きで、それゆえに出来上がったサウンドドラマがあります。
非公式作品ではありますが公認となっている同人作品ですが、クオリティも非常に高く、この漫画のファンなら絶対に買って損はないものだと思います。ボイスは8人出演、効果音などもしっかりとつくりこまれていました。
シーサイドショップでCDとダウンロード版を購入できますが、CD版には声優お二人のアフタートークも収録されています。

罪と罰
刊行 2017年2月9日
おすすめ:
資格を持つ者には手段として殺しも許される

裁弥勒(たちみろく)は大学にも行かず退廃的な生活を送っています。家族の期待に応えて公務員になるか、自分の好きに生きて作家を目指すかのジレンマに苦しみながら。なんにせよ、とにかくいま必要なのはまとまった金です。
ある日、身売りしてる女子高生リサと援交少女たちを斡旋するリーダーに出会い、弥勒の生活は一転します。その売春斡旋業者が売上をヤクザに上納するタイミングを偶然つかんだ弥勒は、その売上金を強奪する計画を立てます。しかし計画実行の際に想定外のアクシデントが発生して、予定外の人物まで殺害してしまいました。
計画通りに大金を手にして証拠を残さずに現場を去りましたが、崇高な目的のために許されたはずの流血は早くも弥勒の精神を蝕んでいきます。

立派な人間とは。品行方正で人に優しく、公正で公平、思慮深く聡明で間違いを犯さない。でも果たしてそんな人間が魅力的でしょうか。傷つきやすく不完全な人間に本物の人間らしさを感じます。誰かと寄り添って生きる、その無様さを受け入れることは、孤高を保って一人で生きるよりよほど強さを求められるのではないでしょうか。
そういった当たり前のようで難しい人間の営みを、なにより尊いものとして問い続けるのが本作の真髄でした。当たり前のことをただ説教くさく説き伏せるだけでは誰も耳を傾けませんが、検事が弥勒を諭すまでには長い物語と思考と感情が激しく渦巻いてます。だからこそ説得力があるのです。
原作の「罪と罰」とはかけ離れた世界観と設定ですが、本質は捉えられていると思います。そして主人公の罪の意識、思想、自尊心などを巡らせながら、葛藤と成長を10巻で描き切ったのは見事です。
- ネタバレ感想を表示
-
【裁弥勒という人物】
いかにも退廃した大学生の汚いワンルームの部屋が見開きで描かれており、これだけで現状の環境を語っているよう。彼の人間性は実はかなり恵まれているのか、周囲の人間の多くが心配していることからもうかがえます。姉、被害者の女子高生、下宿先の娘、大学の友人、街で出会った女性など、みんな弥勒に好意を抱いていました。
それをプライドが邪魔してうまく付き合うことができていなかったのが誇張して描かれていますが、かえってリアリティを感じるのでしょう。このプライドの高さが仇となり、計画的事件で予定外の殺害を犯してしまいます。その際の被害者女子高生を殺す心境が状況だけみれば飛躍が大きく、ここで主人公の気持ちが理解できるかどうかが肝要になっています。
作中で弥勒が冗舌になる唯一のシーンが、ファストフード店で警察巡査と話しているとき。弥勒は巡査を完全に見下しており、なんの気後れも感じていませんでした。このような細かい点でも人物の性格が表現されています。
そして作中後半。弥勒が理屈ではなく気持ちでものを語る場面が増え、その時は瞳にハイライトが入ります。明らかな顔つきの変化からも、弥勒というキャラクターが成長していることが読み取れました。
【首藤という人物】
弥勒がインターンで訪れた会社の嘱託社員。弥勒の唯一の理解者であり、同類ともいえる人物が首藤でした。首藤は欲望に忠実に自由に生きているようで、弱みを握られたある人物に縛られており、強者でもあり弱者でもありました。そして、それをすべて自覚しているから、どこか首藤の言葉には説得力があります。
弥勒は自分が強者側にいることを信じて疑わないところがあったので、二人が似ているようで首藤のほうが一歩先を行ってる印象が分かる点ですね。
生き物の世界に食物連鎖があるように――
人間の世界にも強者と弱者のヒエラルキーがある。
肉食獣が草食獣を糧として食らうことは天から与えられた権利だが――
また同時に使命でもある。
自然がそう命じるならば従う以外に道はないだろう?首藤首藤が歓楽街で弥勒に放った言葉、人間に興味のない人間が人間を描くことなんてできるはずがない、だから空っぽなんだと言い放っています。
「憎しみに任せて殺した。あれほど誰かを憎いと思ったことはない。」人を殺すのにこれほど正当な理由はないよ。これほど人間らしい動機はない。簡潔で美しい獣の論理だ。
事件を起こした弥勒を首藤が肯定した場面。私はこの漫画をもう10回以上繰り返し読んでいますが、初めて読んだときは理解しきれない部分がたくさんありました。少しずつ弥勒の心境が理解でき、五位検事の意図や説得を理解し、知的で哲学的なテーマにはまっていきました。
この世が地獄のような苦しみや泥濘にまみれていても、それでも生きるに値する美しい実感があることを教えてくれる作品です。
JKさんちのサルトルさん
刊行 2021年7月20日
おすすめ:
実存は本質に先立つ。君を縛るものがあるならそれは君が作り出した君の中の真善美という虚像。その虚像の間違いを探し修正し続ける、それが人間になるということだ。 それはときに怖いし孤独かもしれない、だから生きる意味も分からなくなるかもしれないが、それでも楽しいから生きる。

美大を目指す女子高生 巫(かんなぎ)マリオ。
進路に悩む中、ふと川でぶさいくな喋る犬(パグ)を拾います。実存主義者で哲学の巨人ジャン=ポール・サルトルが犬として現世に転生。サルトルさんはパリに帰りたいがここは2021年川崎市。巫家に馴染んでたばこは吸うわ、酒を飲むわ。そんなサルトルさんが巫家の人々のお悩みを解決していく哲学コメディ漫画。
三巻で全体の世界観はつながっていますが、基本的に1~2話で完結するスタイルです。

哲学者サルトルの言葉を、現代人のお悩みに回答する形で漫画にした哲学コメディ漫画。
サルトルの主張が現代的な感覚では絶妙にかみ合わない部分もあるが、毎話短いストーリーの中でうまい返しで問題解決に導いてると思います。小難しい哲学の話というのはなくて、私たちが日常生活の中で感じるよくある悩みを哲学的アプローチで諭してくれるようです。
そんなサルトルがぶさいくなパグ犬の姿で核心的な名言を残すギャップがシュールです。サルトルの性格面も強調されており、特に愛や性の話になると熱くなりすぎて下卑たゲス犬になります笑
哲学は難しいものとして捉えられがちですが、極論考えることが哲学で、普遍的な悩みに対する答えを導こうと努力するのは全て哲学です。そして人は生きている限り必ず悩みます。しかも皆同じような問題で悩むもので、絶対的な回答はないものの、哲学はそれぞれの個人が考える指針になってくれるでしょう。

動画サイトにて新聞紙を頭に被った男が犯行予告をアップロードしました。後日その予告は実行され、その後も新聞紙男による同様の犯行予告が繰り返されます。
警視庁サイバー犯罪対策課は新聞紙男の正体や動機を探るべく本格的に捜査を開始。
新聞紙男が犯行を行う対象はいつも何かしらの悪人への制裁という形をとっており、ネット上では新聞紙男を支持する層が増えてきます。新聞紙男の犯行予告と悪人への制裁は社会現象へと発展し、カリスマ的存在へとなっていきます。

三巻完結と短いながらも非常に綺麗にまとまった漫画でした。新聞紙男の正体、動機、目的、すべてが明らかになった上、最後まで警察も世論も新聞紙男の策の上に転がされます。
犯罪とはいえ世の中の悪人に制裁を与えてだんだんと大衆に支持されていく復讐劇のような構成もすっきりしていいですね。警察から逃れるアリバイ対策もしっかりしており、もはや世間ではダークヒーローのようなカリスマ性を持っていきます。
特に前半は新聞紙男の正体が読者にもわからないうち、どこまでが彼の計算なのか底が見えない筋書きも読んでいて面白いです。そして後半の新聞紙男が生まれる経緯に至った壮絶な過去、犯罪を共有して築き上げた歪んだ仲間たち。
新聞男の根底には社会のすべての搾取される側の人間を救いたい、彼らにも自尊心が必要不可欠でそれがないのは生きている状況とは言えない語られます。

週間コミック誌編集部の新人編集者・黒沢心を中心に、漫画や出版物に関わる裏方にスポットを当てたお仕事漫画。
作家のメンタルや人間関係、編集者の数字へのプレッシャーと個性、売り出し方のSNS戦略など、漫画に関わる人たちの人間模様がリアルに描かれています。また、グラビア撮影、画集出版、美術本など漫画以外の出版物なども取り上げて、出版業界独自の慣習や事情などを分かりやすくストーリーにしています。
二人の新人作家を抱えることから編集者としてスタートした主人公・心は、周囲のベテラン作家や編集者にも支えられながら、作家と共に着実に成長していきます。

全20巻となっており、新人編集者・黒沢心が、発掘した天才新人漫画家をデビュー・連載・アニメ化と成功へ導いていく物語です。同時に作家の仕事面だけでなくプライベートや精神面にも焦点を当てながら、枝葉のショートストーリーもはさんでいきます。
正解のないクリエイティブな仕事をテーマにしているだけに、人物たちの悩みも多いものになります。だからこそ人の心に刺さる名言が頻出します。
作家と編集者が二人三脚で歩んでいく本作。その制作の裏では多くの人の関りや人間ドラマも見えてきます。売れる作品を描く人は良い作品を描くのはもちろん、いかに読者や作品を愛しているか。デビュー後に息長く活躍する人ほど成長と変化があり、人間力に優れ、愛される人なのだと実感します。
- ネタバレ感想を表示
-
【漫画の映像化】
漫画原作を映像化するにあたっての、原作者と制作者の折り合いの難しさが取り上げらました。このセンシティブなテーマは、場合によっては人命に関わるほどの問題をはらんでいます。興行を優先したキャスティング、大御所俳優の使いどころ、原作と脚本の違い、あらゆる大人の事情が絡んでいるのが分かります。なぜ原作通りにならないのか、なぜ設定が変わるのかといった事情が少しだけ理解できました。
【web漫画の台頭】
バイブスでweb漫画誌を始める話が立ち上がった話。連載も単行本化もPVで決定、ジャンルも設けずセグメントの垣根を超えた連載で個人の好みを反映させるという方針でした。しかしまだwebでコンテンツを発信する黎明期で、紙の雑誌に対するプライドなどからも反対意見も少なくない。
そこで部内で数字にうるさいヒール役だったベテラン編集者が「このまま何もしなかったら、紙の雑誌どころか漫画文化自体もなくなってしまう。今、やるべきです。」といって強気でおし進めます。局長にもしっかりと話を通し、企画を通した手腕に感心したシーンでした。
【刀剣美術本プロジェクト】
バイブスの人気漫画家の登場キャラクターにちなんだ刀剣に関するプロジェクト。巷で流行りの刀剣女子を取り込む形で、刀剣に関する美術本を出版することになりました。しかし刀剣は権利関係が複雑で御物や個人蔵など一律ではなく、掲載許可を取るだけでも苦労するもの。掲載料や画像代が高額になることもあるそうです。さらに刀剣は光の芸術でもあり撮影が極めて困難な対象で、新撮となるとさらに費用がかさんでしまう。
このような業界裏話や制作秘話はとても興味深い内容でした。
「重版出来」とは初版と同じ版で刷り増すことで、すべての作家と出版社が好きな言葉。